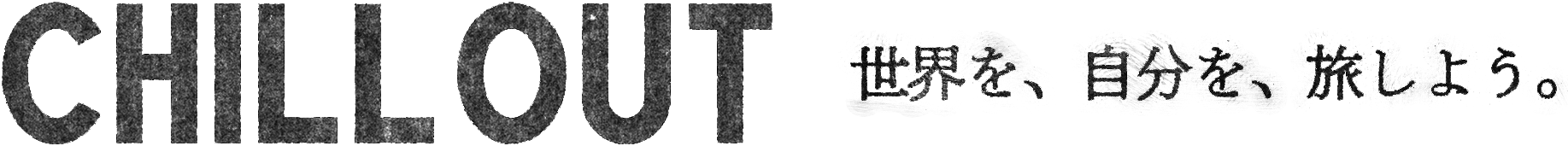オーストラリアには、アボリジニという先住民がいる。
かつてはアボリジニの島だったが、イギリスによる侵略の結果、いまや人口の3%前後という圧倒的な少数派である。
そんな先住民の祖先をもつシドニー生まれの男性と仲良くなり、彼が現在のオーストラリア社会について思うことを聞いた。
二分する「オーストラリア・デー」
さて、彼との話の取っ掛かりは、1月26日の「Australia Day(オーストラリア・デー)」であった。
公式な国民の「祝日」であり、パレード、コンサート、式典、バーベキューといったイベントや祝賀行事が全国で行われるという。
だが、この日は「Invasion Day(侵略の日)」という別名をもつ。欧州から来た最初の定住者が、シドニーに英国旗を立てた日だからである。
先住民にとってはまさに「終わりの始まり」であり、話を聞いた彼は「俺はこの日を決して祝ったりはしない」と渋い顔をするのだった。
いまも残る白豪主義
1958年まで、オーストラリアは「白人主義」を掲げた国だった。
寛容な移民政策により経済成長を遂げた現在、もはや「白人のためのオーストラリア」など決して標榜できない社会であるが、

その名残りはオーストラリアデーを「祝う」と疑いもせず言う多数派の国民にまだ強力に生き残っている
と彼はみる。
始まりは侵略の歴史
帝国主義の時代がはじまる前には、オーストラリア全土で少なくとも250もの言語が話されていたと言われている。
だが、英国による侵略をきっかけとした同化政策の歴史を経て、英語が公用語の現在は、日本人をはじめとするアジア人、ヨーロッパ系、アフリカ、中東など様々なバックグラウンドの移民が暮らすにも関わらず、国民の約8割が英語以外を話すことがない状況である。
強制された“自分のことば”
彼の両親は、学校教育で英語以外の母語を話すことを禁じられ、一言でも母語を話せば、先生から手をはたくなどの体罰を加えられたという。
そうした教育の結果、両親は母語を忘れ、英語によるコミュニケーションしか取らなくなった。
彼も当然に英語が母語となったが、そうした状況を彼は「自分であって自分でない」と感じるという。
彼はみずから母語を取り戻そうと自分で学び始め、先住民の歴史書を、先住民の母語で理解できるくらいには習得したそうだ。
言葉の標準化は個人に対してかように大きなインパクトを与えるものである。
言葉は思考や文化と切り離せない
「俺」「僕」「私」「あたし」「オラ」「わし」「吾輩」…が英語に訳されると全て「I」に統一されて微妙なニュアンスの違いがなかったことにされてしまうように、彼の母語にも
自己紹介をするときはまずは両親から紹介し、その後に自分を紹介する
という英語とはまったく似つかない独自の様式があるという。要は、文法から挨拶の定型文まで、まるきり違うのだ。
(日本人の名前が姓→名の順番なのも、個人よりも家に重きが置かれていることの証であるかもしれない)
彼が日本人に伝えたいこと
そんな彼が、英語を一生懸命に学ぶ日本人に警告したいことがある。



英語はツールであり、アイデンティティは日本語にあることを忘れるな
ということだそうだ。いわく、
英語はbrain wash(洗脳)である
沖縄ことばが禁止された歴史
この話を聞き、私は沖縄の歴史を思い出していた。
明治12年に琉球王国が日本国に侵略されて滅亡したのち、たんなる行政単位のひとつとなった「沖縄県」で進められたのは、沖縄言葉の禁止と標準語の強制という「洗脳」である。
明治40年ごろからは標準語を励行するために沖縄各地の学校で「方言札」という罰札まで使われ出し、ひとたび方言を使えば次に使う人が現れるまで板を首からぶら下げなくてはならない決まりとされた。
私は彼にこう尋ねた。
こうした同化政策が、なにもオーストラリアだけではなく日本を含む世界中で起きた事象なのだとしたら?
彼はこう語った。



当時はただの点だったマイノリティが、インターネットで簡単に同じ境遇の仲間とつながれる現在、もう易々と権力に屈することはしない
ただ、彼は同時にインターネットを憂いでもいる。
事実とは異なる言説が、正しい史実のように語られることが増えたと感じているからだ。



歴史は常にマジョリティに都合の良い方向に修正される
たとえば?



オーストラリアデーはずっと1月26日だったという人がいるが、それは誤りだ。アボリジニの声を受け、過去に何度か変更された歴史がある
だとするならば、これからもその日付は変更可能なのでは?
なにも議論を呼ぶ日を祝日に据える必要はないのでは?



その通りだ。でも、政権はマイノリティを支援しすぎるとマジョリティから嫌われて自分の立場が危うくなる。
結局はマジョリティがマイノリティを潰す構図は今も変わらないのさ
彼は、ビールの入った水滴のついたグラスの底を、テーブルの上の薄いティッシュに何度も何度もぐりぐりと擦り付けていた。



このティッシュはマイノリティで、ビールはマジョリティさ……
彼の口元は緩んでいて、ジョークを飛ばしたつもりだったのかもしれないが、目は笑っていなかった。